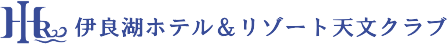12月1月の観望会は、チラシのようになります。日程表はこちらを参考にしてください。 ご案内用PDFファイル
星座の中では、夏のさそり座と冬のオリオン座がそれぞれの季節の代表格ですね。
今回は、季節的にもオリオン座の話。
とにかくわかりやすく、みつけやすい星の並び。
全天で一番かっこよくて贅沢な星座という印象。
黄道から外れているので、黄道12星座には入っていないけど、
それでもこれだけの圧倒的な存在として親しまれている訳を見て見よう。
≪馴染みある星座の形≫
明るい4つの星が織りなす、鼓ともリボンとも呼ばれる窪んだ四辺形の中に、
三ッ星の明確な目印があります。この三ツ星。なんと美しく等間隔に並んでいることか?
と、初めて見たときには感動を覚えます。そのうちに、このきれいに並んだ三ツ星は
ばらばらの距離にあり、(817光年、1340光年、916光年)なんの関連性もない。
でも、地球からみたときだけ、偶然にもこれだけ美しいアステリウム(星の並び)を演出する。
と、こんなことにも感動を覚えます。
≪一等星など明るい星がいっぱい≫
オリオン座には、ベテルギウスとリゲルという二つの一等星があります。
ひとつの星座にふたつの一等星が含まれるのは、このオリオン座と南天の南十字座、
ケンタウルス座の三座です。しかし、オリオン座以外は南天の星座なので、
あまり馴染みはありません。だから、我々日本人にとっては、オリオン座は二つの一等星を
たたえる、とても希少であがめたくなる存在です。さらに続けると、二等星が5つあります。
二等星の数だけなら、北斗七星を持つおおぐま座が6つの2等星で最多なのですが、
おおぐま座には1等星はありません。
なんといっても明るい星が多いということに異存はないですね。
≪ひとつひとつの恒星がそれぞれハイスペックで話題性が多い≫
【ベテルギウス】 (α星)498光年 一等星 実はもうひとつの一等星リゲルのほうが明るい
のに、なぜかこのベテルギウスがα星です。まあ、決まりではないですが、
その星座で一番明るい星がα星となることが多いのですが。
そして、星としての晩年を迎えた「赤色超巨星」という最も巨大な恒星のカテゴリーに
分類されます。星は晩年を迎えると温度が下がり赤くなり巨大化していきます。
現在のベテルギウスは、直径は太陽の1000倍。つまり、太陽の位置へ持ってくると、
木星の軌道までのみこんでしまう、それほど巨大な星です。そして、こうした星は
最後には「超新星爆発」を起こし、星の一生を終えます。2019年ごろから、
ベテルギウスの明るさが変化し不安定になってきたので、超新星爆発が今か今かと
騒がれていました。が、その後「まだ爆発の兆候はない。はやくても10万年後」と
する論文も発表されたことから、その騒ぎは沈静化しています。
という事は、私たちは、このオリオン座の姿は変わらず眺められるという事ですね。
ベテルギウスの存在しないオリオン座など、形無し(肩なし?)想像したくもないですね。
でも、その一方で、冥途の土産として超新星爆発をこの目で見たかった、という思いも。
いずれにしても、私たちが見るものは498年前のベテルギウスの姿なのでしょうが。
【リゲル】 863光年。オリオン座の中で一番明るい一等星ですが、なぜかβ星。
青白く輝く「青色超巨星」。 青白い、という事は表面温度が非常に高温であることを
示していて、12000°。直径は太陽の80倍。ベテルギウスの赤に対比して、こちらは
白いので、和名としては、ベテルギウスを「平家星」、リゲルを「源氏星」と呼んだりします。
さて、このリゲルを語るうえではずせないのが、その巨大なエネルギー。
恒星の放出するエネルギーは。温度の4乗と半径の2乗に比例するとのこと。
リゲルはそのどちらもトップクラスなので、エネルギーは膨大。太陽の12万倍。
さらに、このリゲルは、主星リゲルAとリゲルB、Cの三重連星、さらにリゲルBは
Ba,Bbの連星(分光連星)。しかし、A,B,Cは、実視連星とはいうものの、
伊良湖の口径15cmの望遠鏡では、まずこの複数の恒星を分離して見ることは難しいです。
よほど、すべての条件がそろった好条件の日に、なんとなく二つに分離できているような
気にはなりますが。
≪有名な星雲などの宝庫≫
恒星だけではありません。オリオン座は星雲の宝庫でもあります。
星雲とは、星と星の間に位置する星間物質が近くにある恒星などの光を反射したり、
恒星の影響で周りのガスやチリが熱くなったりという具合に、星間物質が何らかの方法で
光って見えるものを言います。
有名な星雲【オリオン大星雲】をはじめ、【馬頭星雲】【火焔星雲’燃える木’】【ランニングマン星雲】
【モンキーヘッド星雲】と枚挙にいとまがないほどです。が、一般の望遠鏡で手軽に観察できるのは、
オリオン大星雲で、そのほかのものはなかなか難しく、カメラの機能と望遠鏡の機能を併せ持った、
電視望遠鏡で観察すると、こうした星雲に手軽に出会えます。
【オリオン大星雲(M42)】
これは星雲の王者と言って過言ではないでしょう。まず、大きい。
星雲で肉眼でも見ることができるのは、まず、このオリオン大星雲です。
三ツ星の南(下)では、細かい星が縦に並んで小三ツ星を作っています。
この中央の星を見ると、なんとなくにじんでいるように見えます。
これが「オリオン大星雲」と呼ばれる巨大な星雲です。
双眼鏡や望遠鏡では鳥が翼を広げた姿に見え、幻想的で美しい世界です。
また、もわっとした星雲の中に、きらきらと輝く星たちがいます。
なんとも生命力を感じる星の輝きです。この星たちは誕生して、まだ!200万年
程度しかたっていません。太陽の46億年とくらべると、まだ赤ちゃんの星と言えます。
この星雲の中では今も星が次々と誕生しているのです。まさに星のゆりかご。
この赤ちゃん星の中でも、小さな台形に形づくられたトラペジウムという4つの星は、
見つけると、ワクワクした気分になります。


【火焔星雲’燃える木’ NGC2024 Flame Nebula】
散光星雲。場所はちょうどオリオンのベルトの三ツ星の一番左の星、アルニタクのすぐそば。
名前がいいですね。。火焔星雲、燃える木と呼ばれ、まさに、炎の中で燃え盛る木のようです。


【馬頭星雲 IC434】
星雲の種類としては暗黒星雲で、背後にある星の光をさえぎって黒い雲のように見える星雲。
シルエットが馬の頭のように見えることからこの名で呼ばれています。
というように、今回は冬の星座の代表格、オリオン座の紹介をしましたが、
冬の夜空は、そうそうたる星座、恒星、星雲、星団の宝庫で見るべきものが付きません。
寒いけど、寒さに震えながら、その宝石のように美しい世界に浸ってみることはきっと忘れ難い経験と
なるでしょう。一度、伊良湖の天文台まで、望遠鏡をのぞきに来てみてください。
勿論、惑星の花形、土星、木星もその華やかな姿を皆さんに見ていただくべく、スタンバイしていますよ!
観望会へのお申込みはこちらから。