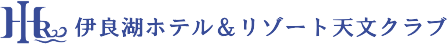10月11月の観望会は、チラシのようになります。日程表はこちらを参考にしてください。 ご案内用PDFファイル
虫の音が聞かれる頃になると、星空の様子も夏から秋へと移り変わります。
今まで天頂近くに鎮座していた夏の大三角が、そろそろお役御免ともいうように西の空に滑り落ち、
東から、秋の星座たちが昇ってきています。 夜の9時頃、真東に向かって空を望むと、「天高く馬肥える秋」をまさに体現しているペガスス座の
四辺形が見えます。代表する4つの星が「秋の四辺形」として有名ですが、実際には「秋の菱型?」
「傾いた四辺形」に見えます。3つの2等星とひとつの3等星(菱形の一番下の星)から成る
傾いた四辺形が望めます。この四辺形は、ギリシャ神話に出てくる翼を持つ天馬”ペガスス”の
胴体部分にあたります。そして、この星座絵は、この胴体だけで、前足は描かれているものの、
後ろ足は描かれていないのが特徴的です。
さて、次にこの四辺形の一番左側というか、北側の星に注目しましょう。 この星は、アルフェラッツという名前で2.07等星で「馬のへそ」という意味です。
ちょうどペガススのへその部分なので当然でしょうが、実は、この星にはこんな歴史がありました。 山の頂上が複数の都道府県にまたがっている、という例は多々あります。
富士山(静岡県と山梨県)白山(石川県と岐阜県)、御嶽山(長野県と岐阜県)など。
これは行政区画の境界線が自然の地形、特に山脈や分水嶺、主要な河川などを基準に定められてきた
ことと関係が深いと思われます。 さて、星についても、同様に一つの星が二つの星座にまたがっていることがありました。 もともと、星座の定義はあいまいで、星座が誕生したと言われる今から5000年ほど前、
シュメール人が特定の明るい星を結んで形を作り、神話上の動物や人物にみたてたものが星座の始まり
と言われています。そのため、星座そのものも境界線はあいまいで、
さらに天文学者や文化によって様々なものが登場し、どうにも整理をしなければならないところまで
混沌としていました。 そこで、1928年の国際天文学連合の総会において、星座とは夜空を区切った領域(都道府県のようなもの)
と位置づけ、星座は88に整理し分けられ、夜空全体を重複することなく隙間なく覆うように境界線が
定められたのです。 そこには、星は、唯一一つの星座にのみ存在することとなりました。したがって、従来星座をまたがり、
複数の星座に存在していた星は、どの星座の星であるか、その唯一の星座が整理し決定されました。 おもなものに、 エルナト(おうし座のβ星) かつてはぎゃしゃ座にも所属していた アルフェラッツ(アンドロメダ座のα星) かつてはペガスス座にも所属していた
といった具合に、整理されました。
エルナトは「角でつく」という意味なので、おうし座所属は納得できますが、
アルフェラッツは「馬のへそ」という意味なのに、アンドロメダ座?と思うところですが、
やはり古今東西、皆、きれいな女の人には弱かったのでしょうか。 さて、アルフェラッツの歴史に触れたところで、このアンドロメダ座についてです。 このアンドロメダ座はアルフェラッツというお姫様の顔の位置の星から明るい星が三つ、
ペルセウズ座のほうに流れています。神話の中では、アンドロメダ姫は、困難な状況を救ってくれた
ペルセウスとめでたく結ばれるのですが、そのお話は別にするとして、
この明るい三つの星(3つ目はペルセウス座の星(ミルファク1.48等星)に注目しましょう。 アルフェラッツのすぐ下の、名前のない3.27等星は見過ごし、ひとつめの明るい星ミラク、2.07等星。
この星をいままでの流れから90度の方向に天頂に向かって方向を変えると3等星が二つあります。
この二つ目の3等星の上あたりにぼわっとした雲のようなものが、条件が良ければ肉眼で見えるはずです。
名古屋市内のような市街地では無理でしょうが、少し郊外へ行くと、肉眼で見えるはずです。
その大きさは満月5個分ともいわれています。 これをかつては、星雲(銀河系内にあるチリなどの星間物質がなんらかの理由で輝いてい見えるもの)
と思われていて、アンドロメダ座にある星雲という事で、アンドロメダ星雲となずけられていました。
しかし、1924年天文学者エドウィン・ハッブルがこれを天の川銀河の外にある 天の川とは別の銀河で
あることを突き止めました。この発見は、ビッグバン宇宙論へとつながる重要な天文学の転換点とも
なりました。そして、これは名前を改め、今では「アンドロメダ銀河」と呼ばれ、
なんと、距離は250万光年です。宇宙の果てからその光はやってきます。 このアンドロメダ銀河は日本から見える最大の銀河と言われています。なお、南半球へ行けば、
大小のマゼラン銀河がみえますので、そちらの方が、視覚的には存在感があるのですが、
実際の銀河としての大きさは、アンドロメダには到底かないません。 というところで、銀河のお話。 私たちの住む地球は、天の川銀河という、太陽のようなみずから光り輝く恒星が2000億個も集まった
とされる銀河の中にいます。私たちが目にする星は、その天の川銀河の中のしかもかなり近くの星を
見ています。ですから、有名な星の距離も シリスス4.6光年、ベガ23光年、遠いとされるデネブでさえ、
1400光年という事で、宇宙の規模からいったら、ごくごくごくごく身近な星を見ているにすぎません。 しかし、ここで、銀河という存在が登場しました。銀河は、(矮小銀河を除き)一番近いとされる
マゼラン銀河でも、大マゼランが16万光年、小マゼランが20万光年です。
16光年、20光年ではありません。銀河の距離には、必ず「万」という数字が付きます。
何百万、何千万光年の先から届く、気が遠くなるような古の光を見ていることになります。
星をみることそのものも、その超壮大な世界に思いを馳せますが、銀河はさらにスケールの違うお話ですね。 さて、アンドロメダ銀河は秋の風物詩です。 夏の喧騒が過ぎ、秋の静けさがやってくると、寝そべって、北東の宙を眺めませんか。
慣れてくれば、きっと、秋の四辺形が見つけられ、アンドロメダ座がわかり、そして、アンドロメダ銀河を
見つけられるようになるでしょう。
壮大な宇宙の果てから何万年という気の遠くなる時間を経てやってきた光のほんの雫を味わい、
その宇宙のスケール感に浸りたいものと思います。
そして、望遠鏡で、250万光年という気の遠くなるような道のりをやってきた光のかけらにのぞみ、
壮大な宇宙に想いを馳せましょう。

M31 アンドロメダ銀河 Photo by Asada
およそ1兆個の恒星から成る我々の天の川銀河に最も近い銀河。(矮小銀河を除く)
銀河の大きさも質量も、天の川銀河の約2倍。250万光年の距離にある。
視直径は約3度(手を伸ばして小指の先が1度)で満月5つ分。
天の川銀河とは、約40億年後に衝突、合体すると言われている。
観望会へのお申込みはこちらから。